2軸歩行
便宜上、2軸歩行と呼んでいます。
が
「2軸歩行(左右軸)」
これが正しい呼称だと思います。
一般的な歩行
脊柱を上下2軸で切り分けて扱う歩行=2軸歩行(上下軸)です。
- 上半身の捻り(上から下)
- 下半身の捻り(下から上)
これが脊柱上で交差します。
「肘を引き、足を上げる」
いわゆる「腕の振り」で歩く歩行です。
力の流れはキネティックチェーンでいう「クローズ型」に近いです。
※1本の軸(背骨の中に)上下軸があるので厳密にはこちらも「2軸歩行」と呼びます。
ミサトっ子おじさんの歩行
脊柱を1本軸として扱う歩行=2軸歩行(左右軸)です。
- 1方向への脊柱の捻り
- 下肢-脊柱ー上肢と連結する
下肢から上肢へと「交差する事のない捻り」が力を伝達します。
力が交差しないので「せん断応力」による関節の負担もなく、ブレーキも無く、力はロス無く伝わります。
キネティックチェーンでいう「オープン型」に近いです。力は常に「カラダを通り過ぎる形」で通過します。
力が循環する
力がカラダを通過した後、カラダは力に引っ張られる形で移動します。
「歩く」というより「動く」という感覚です。
流れる力を邪魔せず、邪魔しない様にカラダを動かすと結果的に「歩く」という行為が成り立つ。
- 主役:「力」
- 目的:「力の邪魔をしない」
- 結果:「歩行動作」
抽象的ですがこの様な感じです。
カラダは常に不安定な状態を移り変わり、結果的に「安定」に近い状態が維持されます。但し、流れを止めると当然カラダは倒れます。
「不安定×不安定=安定」
これが左右2軸歩行の特徴です。
運動生理学で捉えると、「屈曲×外転=回旋」その様なイメージです。
それそのものが直接生まれるのではなく、複数の要素が絡み合い1つの結果に至る訳です。

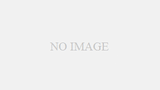
コメント